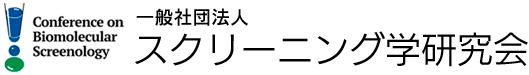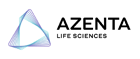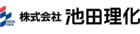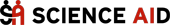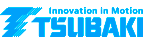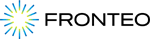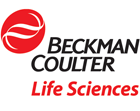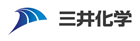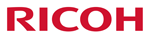【SIG1】HT-ADMET
【SIG2】Advanced Screening Strategy
【SIG3】創薬スクリーニングエコシステムの未来
【SIG4】創薬研究の完全自動化への挑戦
【SIG5】天然物創薬への期待
【SIG6】アッセイデータ管理ツール情報交換
SIG1. HT-ADMET
開催日時
11月27日(木)10:30~15:00 (昼食の提供があります)
ファシリテーター
大塚製薬株式会社 依田 典朗
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Noriaki Yoda,
株式会社住化分析センター 橋本 有樹
Sumika Chemical Analysis Service, Ltd. Yuki Hashimoto
対象者
- ADMET評価に従事している方(20-30名程度)
- 事前アンケートへの回答をお願いします。
- 申込人数超過の場合、1社からの参加人数を調整させていただくなど、ファシリテーターにて調整させていただく可能性があります。
- 積極的に発言してくれる方大歓迎。
- 装置および試薬メーカーの方はご遠慮ください。
内容
実際にHT-ADMET評価に携わるメンバーが日々感じている課題や問題点について話せる範囲で議論・情報交換し、今後のHT-ADMETの発展・研鑽に寄与することを目的として開催します。今年は3つのセッションに分けて情報交換を行いたいと考えています。
- クリアランスのIVIVC解析においてどのような試験系から得られた結果を利用しているか、相関性(予測性)がよくない場合にどのようなアプローチを実施しているか議論・情報交換したいと思います。セッションのなかで、肝細胞代謝やNon-CYPの評価系についても取り上げる予定ですので、試験系の情報交換を目的とした方もぜひご参加ください。大鵬薬品工業株式会社の網藤さんから関連する話題を提供して頂く予定です。
- 日々の試験の依頼(受託)~試験~測定~データ解析などの試験業務のなかで効率化を目指したい部分がそれぞれあると思います。事前アンケートをもとに議論したい内容の募集も交えつつ、アッセイワークフローの効率化に向けた取り組みについて、議論・情報交換したいと思います。Axcelead Drug Discovery Partners株式会社の白井さんから関連する話題を提供して頂く予定です。
- 事前アンケートにより議論したい内容を募集し、要望の多かった議題について、議論・情報交換をしたいと思います。このセッションでは提供頂いた昼食をとりながらの実施を予定しています。
話題提供
大鵬薬品工業株式会社 網藤 惇 様
「血清懸濁下での肝細胞in vitro代謝評価を用いたIVIVCの活用」
概要本発表では、弊社での化合物選択におけるIVIVCの考え方とその中で使用するバリデートされた肝細胞を用いた血清懸濁下でのin vitro代謝評価法をご紹介いたします。
Axcelead Drug Discovery Partners株式会社 白井 由紀 様
「HT-ADMEアッセイワークフローの効率化」
概要リード化合物創製・最適化の段階で迅速な化合物選択を実現するには、多種・多量・短納期・低コストでのHT-ADMEスクリーニングの実施が求められます。
この要望に応えるため、Axcelead Drug Discovery Partners株式会社で実践しているHT-ADMEスクリーニングの各工程(依頼受付~化合物供給~アッセイ~測定~データ解析~レポート作成)における効率化に向けた取り組みを紹介します。
SIG2. Advanced Screening Strategy
開催日時
11月27日(木)12:00~15:00 (昼食の提供があります)
ファシリテーター
理化学研究所 出井 晶子
RIKEN, Akiko Idei
シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社 西垣 敦子
Shionogi Techno Advance Research Co., Ltd. Atsuko Nishigaki
アステラス製薬株式会社 和田 玲子
Astellas Pharma Inc. Reiko Wada
対象者 参加登録を締め切りました
創薬研究に携わった経験がある方、in vitroアッセイ系の構築や実施を独力で遂行できる方、助言・指導する立場にある方など
(実際に手を動かされていない方も大歓迎です)
※定員20人程度
※ベンダーの方々については、参加を制限させていただく場合があります
※定員に達した場合、予告なく締め切る場合があります
※事前アンケートに回答してくださった方
内容
創薬研究の効率化と確度向上を目指し、戦略的なin vitroアッセイ系の構築をテーマに、上級者向けのSpecial Interest Group(SIG)を開催いたします。本SIGでは、薬理評価やスクリーニングにおける最新技術に加え、アッセイ設計の戦略的な考え方や実践的な組み合わせ手法について議論します。
参加者同士が知識と経験を持ち寄り、創薬研究における課題解決と新たな可能性の探索を目的とした議論の場にしたいと考えています。
主な議論テーマ:
- スクリーニング技術の最新動向とその選択戦略
- 確度の高い薬理評価手法の設計と実装
- 新たなアッセイ開発とその応用展開
- アッセイ系の組み合わせと最適化に向けた意思決定プロセス
本SIGでは、参加者が自身の研究や実務経験をもとに、戦略的な視点から具体的なアプローチを提案し合います。専門分野で豊富な知見を持つ研究者・技術者が集い、創薬研究の進展に貢献する新しいアイデアや方法論を模索する場として、ぜひご参加ください。
SIG3. 創薬スクリーニングエコシステムの未来 - 産官学連携の振り返りとネクストステップ -
The Future of Drug Discovery Ecosystem for Compound Screening - Review and Next Steps for Industry-Government-Academia Collaboration -
開催日時
11月27日(木)11:00~15:00 (昼食の提供があります)
ファシリテーター
東京大学 創薬機構 櫻井 政昭
Drug Discovery Initiative, The University of Tokyo, Masaaki Sakurai
大阪大学薬学研究科附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター 坂本 潤一
Compound Library Screening Center, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Osaka, Junichi. Sakamoto
スクリーニング学研究会 妹尾 千明
Conference on Biomolecular Screenology, Chiaki Senoo
対象者 参加登録を締め切りました
参加対象企業(CRO含む)、アカデミア、公的機関などで創薬研究に関わっている方で、スクリーニングに関する産官学連携について活発に議論してくれる方。情報収集のみの方はご遠慮ください。
参加要件アンケートへの回答を必須といたします。
定員30名程度。定員オーバーの場合は基本先着順とします。ただし同一機関からの申し込みが多い場合には調整させていただく場合があります。
内容
「創薬エコシステム」とは、新しい医薬品を効率的かつ革新的に生み出すために、製薬企業・大学・研究機関・バイオベンチャー・政府・投資家など多様なプレーヤーが連携し、知識・技術・資金を循環させる仕組みのことです。
近年では、2015年にAMED(日本医療研究開発機構)が設立され、様々な官主導の取り組みがなされたり、アカデミア創薬の活性化による産学連携など、“創薬スクリーニング分野” においても様々な産官学連携が行われてきました。
本SIGでは、近年の産官学連携の振り返りを通して、未来の理想的な「創薬スクリーニングエコシステム」について議論します。
当日、自己紹介(1分/1人)をしていただきますが、その際に「創薬スクリーニングエコシステム」に期待していることや現在の課題など一言いただきたく、よろしくお願いします。
なお、翌日11月28日(金)開催のWS2「化合物ライブラリの協創」では、関連した話題提供、共通の議論がなされる予定です。本SIGと合わせてのご参加も是非ご検討願います。
話題提供
- 田辺三菱製薬 田中 恒平 様
「3社合同ドラックリポジショニングプログラムJOINUSの紹介」
概要:JOINUS (Joint Open INnovation of drUg repoSitioning) は、製薬3社が共同で国内研究機関(大学、公的研究機関、企業等)へ化合物ライブラリーを提供するドラックリポジショニングのオープンイノベーションプログラムです。JOINUSのこれまでの取り組みを紹介します。 - AMED 山岡 万寿夫 様
「創薬ブースターにおけるスクリーニングマネジメントの変遷」
概要:創薬ブースター事業の中でアカデミアの10以上のシーズのスクリーニングを支援し、また同じチームの他の創薬コーディネーターによるスクリーニングを支援する機会があった。いくつかの課題、特に化合物ライブラリーの選定の課題やPPIスクリーニングの成功率について改善を行い、ヒット取得に結びつけた経験などの情報を共有し、意見交換したい。 - AMED 寺坂 忠嗣 様
「産学協働スクリーニングコンソーシアム(DISC)について」
概要:AMED・創薬支援推進事業では、創薬ブースターにおいて2015年に設立したDISCを活用し、支援テーマの大規模企業ライブラリーを用いたHTSを実施してきた。DISCの概要を説明すると共に、本活動の振り返りや課題、今年度でDISC終了に伴うネクストステップについて話題提供し、議論のきっかけとしたい。 - 東京大学創薬機構 善光 龍哉 様
「BINDS支援による企業導出成功事例と課題」
概要:これまでに実施したBINDSにおける創薬研究支援の成果として、アカデミア発創薬標的からのHit to Lead研究の結果見出したリード化合物を海外製薬企業に導出することに成功した。この成功事例を紹介し、成功の秘訣と今後の課題を議論することにより、将来のアカデミア創薬の発展と迅速化・効率化に繋げていきたい。
SIG4. 創薬研究の完全自動化への挑戦
Challenge of Fully Automated Drug Discovery
開催日時
11月27日(木)10:30~15:00 (昼食の提供があります)
ファシリテーター
東京科学大学/一般社団法人ラボラトリーオートメーション協会
神田 元紀
Institute of Science Tokyo/Laboratory Automation Suppliers’ Association, Genki Kanda
一般社団法人スクリーニング学研究会 笹又 美穂
General incorporated organization Conference on Biomolecular Screenology, Miho Sasamata
対象者 参加登録を締め切りました
創薬研究の完全自動化に関心のある、あらゆる方を対象としております。特に、以下のような方々のご参加を心より歓迎いたします。
- 創薬研究の未来を展望し、生成AIやロボット技術活用の最先端を知りたい方
- 自身の研究や業務に実験自動化・生成AI技術を導入するための具体的なヒントを得たい方
- ラボオートメーションシステムの開発や導入、高度化に携わっている方
- 創薬分野への応用を目指す生成AI・ロボット技術の研究開発者
- 所属や専門分野の垣根を越えて、異分野の研究者・技術者とネットワークを築きたい方
- 「AI科学者」が実現する未来の創薬研究のあり方について、多角的な視点から深く議論したい方
※参加にあたりアンケートの提出を必須とします。
※参加者多数の場合には、1機関あたりの参加者数を制限することがあります。
参加人数40名程度
内容
本SIGは、一般社団法人ラボラトリーオートメーション協会(LASA)とスクリーニング学研究会の共催により開催されます。近年、生成AIやロボット技術の進展はめざましく、創薬研究の現場にも大きな変化が訪れようとしています。LASAには、「生成AIが仮説を立て、ロボットが実験を行い、生成AIが論文を執筆する」といった、いわゆる“AI科学者”の実現に向けて研究開発を進める研究者や、その基盤となる自動化技術の開発者が多数参加しています。
実際に情報科学分野では、生成AIが執筆した論文が国際会議で採択される事例も出始めており、生命科学分野でも同様の動きが現実のものとなりつつあります。本SIGでは、創薬研究の完全自動化に向けたAIやロボットの現在と未来について紹介し、ファシリテーターや話題提供者を含む参加者全員が自由に議論・交流できる時間を設けます。また、参加者同士の交流を深めるための自己紹介の時間も予定しています。
プログラム予定
10:30-11:30 話題紹介セッション①
11:30-12:30 参加者自己紹介・昼食
12:30-13:00 休憩
13:00-14:00 話題紹介セッション②
14:00-15:00 自由討論
10年以内には、世界中のどの科学者よりも賢いAIが個人のスマホに入る時代が到来すると想定されます。その世界における創薬研究はどのようなものでしょうか。未来指向の議論の場を提供します。
なお、本SIG終了後には同会場にて、本SIGに大きく関係するAI分野のセミナーが開催されます。合わせてお楽しみください。
話題提供
本SIGでは以下の話題提供を行います。
- 総論・基礎知識の視点から(東京科学大学 神田元紀)
- 生物学実験の視点から(理化学研究所 加藤月)
- 化学・材料実験の視点から(ラボラトリーオートメーション研究会 西田理彦)
- 解析・計画・AIの視点から(理化学研究所 尾崎遼)
- 動物実験・非モデル動物の視点から(筑波大学 史蕭逸)
SIG5. 天然物創薬への期待
Expectations for natural product drug discovery
開催日時
11月27日(木)10:30~15:00 (昼食の提供があります)
ファシリテーター
日本医療研究開発機構 藤江 昭彦
AMED, Akihiko Fujie
エーザイ株式会社 勝俣 良祐
Eisai Co., Ltd., Ryosuke Katsumata
日本医療研究開発機構 新井 好史
AMED, Koshi Arai
対象者
【経験者】
- SNAP“天然物創薬研究会”(Study Group on NAtural Products Drug Discovery)に所属している企業または会員の方
- 上記の所属以外の方は、必ず、参加登録前にファシリテーターに連絡して、参加の了解を得てから参加登録してください。事前の了解がない場合は参加できません。
連絡先: 新井好史 karai (at) earth.email.ne.jp ←の(at)を@に変えてメールにてご連絡ください。
定員35名程度
内容
本会の目的は、創薬研究を取り巻く環境が激変する中、天然物からの創薬に関する技術向上や課題解決を図るため、会員または参加者相互の情報交換・意見交換・技術交流等を行うことにあります。
今回、二人の演者(山形大学 浜本洋先生、演者未確定)より、カイコ感染モデルを用いて発見した二つの天然物の紹介と天然物創薬における課題を語ってもらい、参加者と天然物創薬に関する意見交換を実施する。
- 新規MRSA治療薬の創薬研究(山形大学 浜本洋)
- 新規抗真菌物質の発見(演者未確定)
- 質疑応答
- 天然物からの創薬に関する技術向上や課題解決を図るための情報交換、意見交換、技術交流等
話題提供
- 新規MRSA治療薬の創薬研究(山形大学 浜本洋先生)
- 新規抗真菌物質の発見(演者未確定)
SIG6. アッセイデータ管理ツール情報交換
Exchange Meeting for Assay Data Management Tools
開催日時
11月27日(木)10:30~15:00 (昼食の提供があります)
ファシリテーター
第一三共株式会社, 三井 郁雄
Daiichi Sankyo Company Limited, Ikuo Mitsui
田辺三菱製薬株式会社, 大野 研
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Ken Ohno
対象者
- Activity Base、Screener 、Signals VitroVivo(ABC順)などを使っているエンドユーザーの方。ベンダー様は各社代表1名の参加調整をお願い致します。
参加要件事前アンケートへの回答
定員20~25名程度 先着順
内容
Activity Base、Screener、Signals VitroVivo(ABC順)などを実際に使用してHTSなどのデータ解析を行っているエンドユーザー研究者同士で情報交換を行い、効果的な活用方法を見出すとともに、新たな気づきを得ることで、これらソフトウェアの活用範囲を広げることを目的とします。
これらのソフトウェアを100%活用できているエンドユーザーはほとんどいないと考えられるため、同一ソフトを使用している研究者間で具体的な使用方法を共有し、最大限の活用を目指します。また、各ソフト間の違いを明らかにすることで、メーカーへの機能改善や開発要望の提案にもつなげたいと考えています。