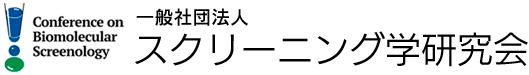村松 康範(第一三共株式会社)
勝俣 良祐(エーザイ株式会社)
新井 好史(日本医療研究開発機構)
10名
概要
天然物創薬をテーマとしたワークショップ(以下、WS)は7度目の開催である。昨年度は「ポストCOVID-19時代に天然物創薬はどのように進展させるべきか」と題して、主に感染症シーズを充足するための「ライブラリー」と「スクリーニング」に焦点を当て、ディスカッションした。
本年度は、有望なリード化合物が見いだされた後の薬剤開発についての議論を深めることを主眼とした。全体講演でご講演頂いた蓮見先生に本WSにもご参加いただき、薬剤開発に関する先生のご経験や教訓などについてお話しいただくこととした。なお参加者はファシリテーターおよび蓮見先生を含め総勢10名であり、その内訳は企業、国、アカデミア等であった。
本WSでは、参加者全員による自己紹介ののち、本会の趣旨説明を行った。自己紹介では、各参加者が天然物に対し、どのような興味をもって本WSに参加したかなどを語ってもらった。特に、微生物資源について興味があることなどのコメントがあった。ファシリテーターからは、蓮見先生のSMTP化合物が、国内ではなくて海外の企業で実用化が有望になっていることを受けて、導出のための資料をどう作成するのか、導出を受ける企業側としてどう評価するのか等の難しい課題があるだろうとのコメントがあった。
続いて、蓮見先生に全体講演での発表スライドとは別に、SMTP化合物の導出のために企業への説明にこれまで用いたスライド等を利用してご発表頂いた。先生のご発表内容を以下に要約する。先生は当該化合物導出のため、国内外合わせて50社ほど回ったが、ほとんどが門前払いか、当該薬剤開発に否定的な意見と共に謝絶されるケースが多かった。そのような状況下、数社のみが興味を示し、特にバイオジェンはデータの詳細をよく理解してくれ、非常に前向きな議論ができた。バイオジェン訪問以前で、ノンコンの資料だけでは理解してもらえないケースが多かったが、バイオジェンへのプレゼンテーションでは実際の実験結果も含んだ詳細データも活用したことが奏功した。また、最近の研究によりSMTP化合物が、血栓溶解の作用機序であるプラスミノゲンのコンフォメーション変化と独立して、sEHの阻害を介して抗炎症作用を示すことが明らかとなり、そのメカニズムを説明することで売り込みが容易になったことも奏功の要因となった。導出成功のカギは、プレゼンテーションの受け手側がその社内で経営判断のできる有力者であることや、当該薬剤のメカニズムを深く理解できるサイエンティストの素養を持っていることが必要である。
先生のご発表の後に参加者全員で机を囲んで総合討論を行った。先生の事例を含め、天然物から画期的な薬剤が発見されるときはフェノタイプスクリーニングで見いだされるケースが多く、薬剤の発見の後に新たなメカニズムやターゲットタンパク質が明らかになることが過去の例からうかがい知れる。そのための薬効をしっかりと評価できるモデル構築の重要性に関しても話題となった。また、天然物から見出された薬剤の研究を通じて、その周辺のサイエンスが進展することが天然物創薬の素晴らしさの一つであるという議論があった。天然物は、生物が36億年という期間の中、生存の上で作り出す洗練された物質で、その産生には何らかの意味がある。その意味を深く洞察・理解したうえで、創薬に応用することが天然物活用のひとつの道筋になり得る。天然物というモダリティをどのように活用するべきか、各参加者の持つ経験・専門性から多角的に意見が飛び交い、特許戦略についての言及もあるなど有意義な議論となった。