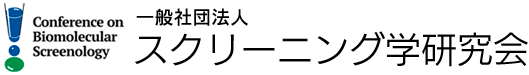竹田 浩之(愛媛大学プロテオサイエンスセンター)
小祝 孝太郎(杏林製薬株式会社)
長谷川 司(東京大学創薬機構)
16名
製薬企業 14名
大学など研究機関 2名
概要
ワークショップの目的と進め方
今年は膜タンパク質に話題を絞り、各々の使用目的に適した発現手法やタンパク質の設計、研究ツールの活用について参加者間で経験や情報の共有・議論した。また、参加者事前アンケートの結果に基づいて、参加者が現在抱えている問題点の解決策についても議論。議論や情報交換を通じて、参加者それぞれが、課題に対するヒントを得られること、さらに膜タンパク質生産について語り合える仲間・つながりをつくっていただくことが目的。
WSの進行と議論内容
前半は2グループに分けディスカッション。自己紹介もかねてご自身の膜タンパクの使用用途や困っている事等に関し自由に発言。その後グループ間で話題紹介しあった
チームA;
グループAは探索のために膜タンパク質を生産したい参加者の割合が多かった。膜タンパク質生産の戦略を立てる際に考慮すべき項目とその優先度について、議論を行った。膜タンパク質の用途(スクリーニング、構造解析、機能解析、ASMS、SPR)、必要な量、必要な品質(純度、活性)、最終的な形状(VLP、ミクロソーム、リポソーム、ナノディスク、ミセルetc。)、発現系、精製法、変異導入の必要性、一過性か安定発現株か、などが検討項目として挙げられた。しかし、唯一の正解と呼べる解答はなく、必要な用途の要求に合わせる必要があることが議論された。とくに顕著だったのが、探索のために膜タンパク質を生産している方が紹介された探索のためにミクロソーム画分を生産するケースであり、その場合は純度は考慮の対象にはならず、量や活性の優先度が高くなる。この議論は機能構造解析のために酵素の精製、生産にずっと取り組んできたという参加者にとっては全く想像の範疇外であったようである。膜タンパク質の生産の担当者と使用者の間に、このような不幸な意識の食い違いが生じないことが非常に肝心であり、そのために事前の議論で生産方法や用途、必要な要件についてしっかりと議論すべきである。議論では、用途、形状、量、質、発現系、精製法の順で優先、重視すべきだろうと話し合った。
チームB;
バックグラウンドが構造解析4名、機能解析5名。発現系の宿主選択やタグの付け方、ターゲット配列はフルレングスかトランケートか、変異体を作った時の性状確認の方法に話題が集まった。
とくに宿主の選択においては、アンケートでは哺乳細胞が多かったが、その理由として収量は少ないかもしれないが多くのミュータントを作るのは法規制も含めラクなことがあげられ、一方昆虫細胞では組換えの制限があり、作製に時間はかかるが、一度ウイルスが取れてしまえば気楽で使い慣れている、収量が稼げる等々と、それぞれ目的による利点があることが議論された。
安定なタンパクを取るためには、タグの検討は付加する位置も含め試すしかないという事が話題になり、なかには百種類ぐらいの変異体を作った経験のある強者もいらっしゃった。
膜タンパクに特有な手法としては、FSEC、FSEC-TSの利用、特にGFPをC末につけるのが、精製時も楽で、変異をかけて安定なタンパク配列を探す場合の評価法として、便利に使えることなどが紹介された。
後半は全体でディスカッションを行い、参加者からの相談事項について議論した。
膜タンパク質の精製において留意すべきことについての議論では、精製度合いはアッセイ方法に依ることを再確認した。探索では精製せず膜画分で使う場合もある(ミクロソーム)。タグは除去するのが一般的だが、クライオ電顕であればサイズ大きめのタグをつけて分子量を稼ぐこともある。N末につけるかC末につけるかも、構造未知であればひたすら何種類も試す場合もある。最後まで翻訳されている事の確認にC末につけるという意見も出された。
保存方法に関しては膜に埋まっていれば充分安定なので、凍結融解は繰り返さないが小分けにして一気に凍らせて問題ないとする意見、クライオ電顕に使用する場合は凍らさずに出来立てを使う必要があったという経験などが紹介された。
膜タンパクを利用するアッセイでは、酵素活性で評価が可能な膜酵素以外では、 SPR、環境が許せばASMSを選択することが提案された。結合すれば機能を持つのだろうかという疑問点においては、結合しなければ機能が出ないだろうからまず結合するものを探す、という考え方が議論された。
まとめ
参加者は、タンパク取りはそれなりにやっているものの、膜タンパク取りは手を付け始めたところという人が多かったが、ディスカッションを通じ、膜タンパクでも可溶性タンパクでも、生産戦略で考えることにそれほどの差はなく、つまりは、同じようにいろいろなことを考え試さなければならず、明らかに異なるところはLysisして超遠心で回収する段階か・・・、という認識に至った。また、多くの参加者の方にタンパク質を作ること、使うことに王道はなく、適当な参考書や成書もないことから、経験や知識を総動員して問題を解決していく必要があることを再確認した。経験を出し合って、使いやすいプロトコール集のようなものを作成出来たらという話題も出た。