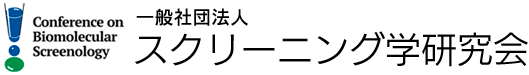池野 雄高(第一三共株式会社)
中納 広一郎(大正製薬株式会社)
長門石 曉(東京大学)
28名
概要
本ワークショップでは事前アンケートの結果から下記の3つのグループに分かれて意見交換を行った。
① 「これから物理化学測定を行いたい」
本テーブルではこれから物理化学測定を行う上で気になることや分からないことについて情報交換を行った。特にSPRに関する質問が多く、第一選択がSPRとなる点が共通していた。固定化条件や得られるデータの解釈に関する意見交換が出てくる中で、いかにして蛋白質を安定に保つかがポイントであることが論点として挙がった。またITCを活用したエンタルピー選抜について、PPI阻害剤探索における物理化学測定の活用方法、質量分析はどのような位置づけにあるのか、について意見交換がなされた。
② 「複数手法から得られたデータをどう解釈するか」
本テーブルでは様々な手法から得られたデータの取り扱いについて討議した。参加者の多くは複数の物理化学測定手法が利用されている環境で創薬に携わっており、各々の物理化学測定手法で得られたデータの解釈や物理化学測定手法以外のデータとの比較を中心に討論が行われた。例としては、合成展開を進めている中で複数の物理化学測定手法で得られたKD値や細胞評価系等で取得されるIC50値がパラレルに推移しない場合、また複数の物理化学測定手法で陽性/陰性の結果が合致しない場合について討論を行った。得られているデータの状況を共有したのち、どのような要因が考えられるのか、どのような判断基準を持っているのか、どの物理化学測定手法を信頼するのか等について、各々の参加者の経験や知識を基に情報交換を行った。また物理化学測定手法の検出限界際の対応方法や各手法のPros/Consについても意見交換が行われた。
③ 「創薬全体の流れにおける物理化学測定の位置づけについて」
本テーブルでは、主に創薬全体の流れを俯瞰した目線からの議論が行われた。Biophysical assayが求められる場面が多様化していることについて、それぞれのケースに応じた各測定技術の使い分けについて理解を深めた。またセルベースやin vivoアッセイとの関連について、biophysical assayにターゲットエンゲージメントが求められるケースや、うまく薬効とブリジッグ出来ないケースなどについて話題となった。プロジェクトの進行に合わせてデータを得ることができるスピード感も重要であるという共通認識も得られた。その他、slow binder、天然変性蛋白質、巨大複合体、蛋白質以外(核酸など)との結合など、難しい評価が増えているということも話題に挙がり、複数のモダリティへの対応も含めて創薬環境の変化にキャッチアップできるbiophysical assay技術が求められていることを再認識した。