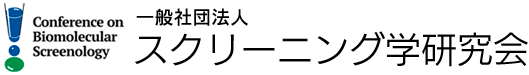ファシリテーター
沼澤 香穂里 (株式会社中外医科学研究所)
内田 実 (ジェノスタッフ株式会社)
生田目 一寿 (アステラス製薬株式会社)
見月 俊吾 (塩野義製薬株式会社)
参加者
34名
概要
WS4 細胞アッセイの自動化では製薬等企業を中心に、アカデミア、公的研究機関など様々な分野から34名の方に参加いただき、製薬企業の方からの情報提供を参考に、細胞自動化の設計・導入・運用等に関して議論した。以下、進行概要および頂いた意見を中心に列記した。
① 細胞自動化の事前アンケート結果まとめ共有
② 中外医科学研究所・井出様からの自動細胞継代装置の導入事例の情報提供
③ グループディスカッション(5グループに分かれて議論)
④ 各グループからの議論内容の発表(以下、概要)
-
細胞アッセイ自動化の初心者向け導入戦略
-
初期投資は、小さく初めて拡張していくか、戦略的に大きな投資からはじめるかの二つの方法がある。スペースの確保、インテグレーション規模の確認も重要。自動化の際に実験プロトコールや原理の理解は必要。
-
-
コスト対効果を最大化する自動化の実践方法
-
コミュニティを拡大し、利用者からのニーズを反映させて、システムを最適化していくことが重要。
-
メインユーザーを増やし、フル稼働させる。職人技の実験を自動化することが誰でも同じ実験を再現できるようになるため価値がある。
-
-
ユーザーフレンドリーな制御ソフトの設計と活用
-
自動化ソフトウェアには、ユーザーフレンドリーで良いものもあるが、カスタム作成ではバグも発生し、トラブル毎に修正してもらう必要がある。ヒューマンエラーもトラブルの原因となり、わかりやすいマニュアル作成も重要。
-
複雑なソフトウェア開発はメーカーに依頼。簡単なものは既存ソフトの機能でユーザーが作成。
-
使いやすさの定義は研究者に依存するため目線合わせが必要。メーカーやエンジニアの対応の良さもユーザーフレンドリーであるかに関わる。
-
可変性・自由度の高さは欲しいが固定されたプログラムの方がエラーは少ない。トラブルの経験はプロフェショナルの育成にも重要。
-
-
HTS・iPS細胞実験における自動化の最新トレンドと課題
-
薬理試験への活用において、機器封じ込めのためのSafety cabinetのサイズは広い方が良い。細胞洗浄を対応する機器をLiquid handlerにするか、Washerにするか。などが選択肢としてある。
-
細胞継代において、攪拌しながらのムラの無い細胞播種、細胞の剥離・回収、さらにコンタミをさせないで細胞の品質を管理していくことは難易度が高く課題。臨床検体の管理も課題。
-
iPS細胞の培養は繊細かつ精密な操作が必要であるため自動化との相性がよい。自動化には初期コストがかかるものの、人が行うよりも再現性が向上する可能性が高いため、長期的には自動化のメリットが大きいと考えられる。
-
細胞播種の自動化は多くの参加者が分注機で実現していたが、スケールアップ時のプレート供給の自動化(スタッカーやハンドラーの導入とスペースの確保など)が次の課題となっていた。
-
-
自動化システムの柔軟性とスループット向上の両立
-
将来的な拡張性を残しておくか、夜間運転のエラー対応をどうするか、ロボットハンドラーによる搬送時間が律速であることが課題。
-
⑤ まとめ
各グループでの議論内容は多岐にわたったが、システムを導入する前に実験のどの工程を自動化するのか見極めておくことが重要という意見は共通していた。この見極めを適切に行うためには実験自動化に関する基本的な知識を有しておく必要があるため、スクリーニング学研究会のようにオープンな議論ができる場は重要である。今後細胞アッセイの自動化に関するチュートリアルを開催し、今回の議論内容を更に発展させていきたい