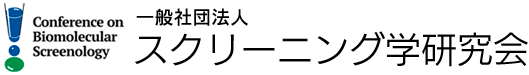出井 晶子(国立研究開発法人理化学研究所)
今村 理世(東京大学大学院薬学系研究科附属創薬機構)
坂本 潤一(大阪大学薬学研究科 附属化合物ライブラリー・スクリーニングセンター)
26名 (ファシリテーター3名を含む)
内訳:製薬企業 18名、大学など研究機関 8名、その他(CROなど) 6名
概要
募集要項
経験:経験不問・スクリーニングに興味のある方 (ただし、過去にこのWSへの参加経験のない方を優先)
内容:
スクリーニングカスケードの構築方法や考え方について、広く学びたい方
タンパク質間相互作用(PPI)のヒット選抜や化合物の絞り込みカスケードに、疑問や不安を感じている方
目的にあったプロファイルを持つ化合物を取得するための「化合物の絞り込み」にこだわりたい方
魅力あるヒット化合物を選抜するためにどのようなアプローチが有効かについて議論したい方
内容
WSの狙い・目的
本WSでは、議論を通じて自分たちでスクリーニングカスケードを組み立てることにより、研究テーマの方針を踏まえて戦略的にスクリーニングカスケードを立案・構築することの重要性について理解を深めてもらうことを目的としている。昨年に引き続き標的分子としてタンパク質間相互作用(PPI)を題材に取り上げ、PPIを標的とする阻害剤探索を対象とする架空プロジェクトを対象に議論を進めることにした。
事前準備
昨年作成したチュートリアルを事前に視聴してもらうようにした(参加者の動画視聴状況については未確認)。また、参加者へ事前資料を送付して、当日の議論を進めやすくした。また、事前アンケートで寄せられていた質問事項に対して、ファシリテーター3名で回答集を作成し、当日印刷物を配布した。
当日の流れ
事前アンケートの結果をフィードバックした後に、スクリーニングカスケードを構築する架空の研究テーマについての詳細やWSで使用する用語の定義など、事前配布資料に従って説明した。 その後の60分間を、スクリーニングカスケードを構築するための議論の時間とした。参加者は、あらかじめ班分けした3班(A, B, C)に分かれて、議論を進めた。今年は、最初に各班に、「どのような化合物/薬剤を創製したいのか」といった簡易的なTPPを作成してもらうことにより、方針を決めた上でカスケード構築を進めてもらった。
次いで、各班で構築したスクリーニングカスケードについて、代表者から3分間で発表、2分間で質疑応答を行った(発表順 B→C→A)。1次スクリーニングで、TR-FRETのセルフリー系を適用したB班に対し、A、C班は細胞の発光系を用いるなど、いろいろな視点でカスケードが構築されていた。各班の質疑応答では、先行品の情報からマウスとの種差が懸念されるが種差試験を実施しないことに対する質問に対し、ヒトの受容体をノックインして使用するという回答や、どのタイミングでメドケムが参加するのが良いかという議論など、興味深いものが多かった。発表終了後に、最も理想的だと考えられるスクリーニングカスケードへの投票(1人1票、自班以外に挙手)を行った。最も票が集まったのは、A班のカスケードであった。 年々参加者のレベルが高くなっており、各班から柔軟で示唆に富んだカスケードが提示されるようになったように感じる。そのため、今年は、定説的とも思われるファシリテーター考案のカスケードを提示することは控えた。限られた時間内で、カスケードを作成し、発表まで行うのは、かなりタイトであったが、有意義な議論ができたのではないかと思う。
まとめと感想
HTSから創薬につなげていくためには、どのようなプロファイリングの化合物を取得したいのかをきちんと考えて、戦略的にスクリーニングカスケードを構築する必要があり、化合物の絞り込みにどんなアッセイ系をどんな順序で組み合わせるかが重要であることを共有した。今回は、「どのような化合物を取得したいか」を最初に各班で議論したことで、方針と戦略のリンク・整合性を考えやすくできたのではないかと思う。
参加者は、スクリーニング初心者・初級者が約半数を占めたが、スクリーニングカスケードの大まかな流れは、ある程度認識できて、戦略を立てることができていた。参加者の経験や専門性を活かした議論がされていた。