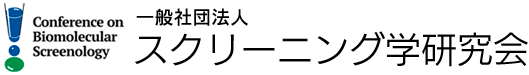広川貴次(筑波大学)
髙宮万里(東京大学)
鈴木秋一(エーザイ株式会社)
23名
概要
WS目的
持続可能な化合物ライブラリー共同利用の実現には、産学の連携が必須であり、ライブラリー活動に関する相互理解の機会とする。
議論内容
【開催趣旨とアンケート結果の共有】
参加者への事前アンケートを実施し、結果の説明をした。
【広川教授より話題提供】: 「共有化合物構造データベースを利用したインシリコスクリーニング」
国内共有化合物ライブラリーDB現状の情報、解析結果を共有された。アカデミア創薬支援を目的としたBINDS主導によるアカデミア所有化合物ライブラリーの統合活動についても説明された。
各大学の化合物ライブラリー、および企業コンソーシアムライブラリ―(2例)のケミカルスペース(PCA)解析結果が共有された。
ケミカルスペースだけで、ライブラリーの良し悪しの考察できないため、同一テーマにおける大学ライブラリーと企業コンソーシアムライブラリ―双方からのインシリコスクリーニングの結果PCA解析ではわからないライブラリーの特徴がみられる例が示された。
各ライブラリーには各々特徴があり、どのライブラリーが良いと言えるものではない。連携することで日本ならではのライブラリーとなる可能性がある。またインシリコスクリーニングではDBを共有しできる限り広く評価できることが重要であると考察されていた。
【まとめ】
広川教授の話題提供により、アカデミアの取り組みにも触れ産学相互を理解する機会になった。
化合物ライブラリーの多様性の具体的比較、具体的テーマにおけるスクリーニング結果への化合物ライブラリー選択の影響が示されケミカルスペースの広さだけが重要ではなく、目的により選択できるライブラリー共有の有効性が改めて確認された。そのため構造DBコンテンツを考えると全ての構造を一括で閲覧できるシステムの構築が有効であると考えられた。
構造情報を開示する際の方法について選択肢を設けることも議論され、構造情報の暗号化の可能性や、部分構造開示のみでもインシリコスクリーニングに有用であると言及された。
化合物構造の開示に対するインセンティブを考えると、産学で広く共有するにはどこまでギブ&テイクを成立させるかが重要になる。インセンティブに関する課題を解決し、産学が一枚岩となってオールジャパンエコシステム構築のための情報共有を今後も継続していくことの必要性を確認した。